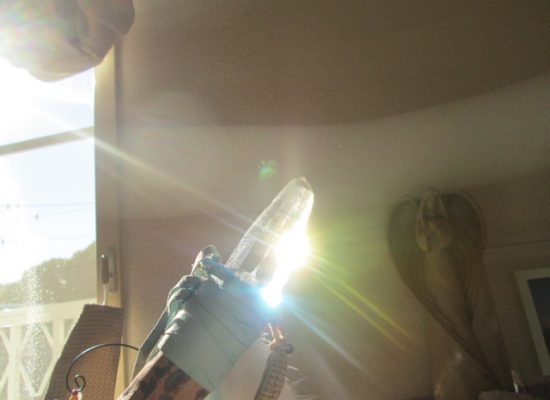鬱状態の時によくあるような、 意欲がわかない、何もする気が起きないといった 慢性的な無気力には、必ず原因があるはずです。
そもそも、人は健全な状態であれば、あれがしたい、これがしたいという興味や意欲が自然にわくものです。子供がいろいろなことに生き生きと興味を示し、やってみたがるのと同じですね。
無気力に陥っているということは、だいたい、心身のエネルギーを使いすぎて枯渇しているか、使わな過ぎて停滞しているか。いずれかだと思います。
例えば、肉体を酷使し、疲れているのに体のサインを無視して頑張り続けたら、いつか必ず燃え尽きて、これ以上何もしたくなくなるでしょう。それは、このまま活力を消費したら病気になるため、強制的にストップがかかった状態であり、肉体の叡智の計らいです。
また、意思に反してやりたくないことないことばかりしたり、言いたいことを我慢し続けたり、自然な感情を無理やり押さえつけて閉じ込めたりしていると、心のエネルギーは低下します。人の悪口を聞かされていると気持ちが下がるように、無意識に自分の悪口を言い続け、 不当な自責感を抱きやすい人も、心のスタミナが足りない人になってしまいます。
自己犠牲的に人の為に尽くし、人のニーズは満たすけれど自分のニーズは顧みない人をよくお見かけしますが、これではやはりエネルギーのアンバランスが蓄積し、 いつか燃え尽きて鬱状態になるでしょう。
これもまた、よくあるケースですが、自分の心が望んでいるからではなく、人に嫌われないよう、社会ではみ出さないよう、自己防衛の為に周囲に合わせて生きていると、長い間にはエネルギーが枯渇し、意欲がわかなくなります。 このような自分の自然な心に対する無理強いは、恐れにフォーカスしているときに起こりがちですが、結局のところ自らの創造性を枯渇させてしまいます。そうなると、本来誰にでも備わっている何かを生み出す力が発揮われなくなるので、何かをしようという気にもなれなくなります。
これに対して、自分の心に沿った言葉や行動、感情を押さえつけずありのまま認めて受け入れること、心が喜ぶ選択など、自分を慈しみ、大切にする行為は、エネルギーを増やし、意欲をアップさせます。
心を縛るのではなく、自由に解き放って、心の方向に従っていると、創造性がのびやかに発揮されますので、結果として、環境が自分にフィットするように整い、自分にとって一番いい方向に人生が展開していきやすくなります。
一方で、十分なエネルギーがあるのにそれを使わないでいると、出口を失った未消化のエネルギーが自分の中でくすぶり、古くなってと滞るため、どんより重苦しく感じられるようになります。 体が元気なのに、恐れや不安ゆえにいつまでも引きこもって活動しなければ、心身の代謝が悪くなり、元気を失って無気力になります。 自分の中にあるエネルギーはちょうどよく使うことで巡り、新たに湧いてくるものです。1日働いてほどよく疲れれば、夜寝て朝回復し、また元気に1日を始められるというわけです。
自分の中に発生した思いや感情があるのに、表現したり、認めずに抑えてしまう行為もまた、未消化のエネルギーを生むので、心身の停滞を起こし、無気力な抑うつ状態を引き起こしやすくなるものです。相手に伝える、伝えないは別として、安全に表現し(それが相手を傷つけるような思いであれば、日記に書く、当事者ではなく第三者に話すなどが安全な方法の例ですね)、自分の気持ちを否定せずありのまま受け入れるなどすれば、内側でくすぶらず、自分の外に解放されていきます。そうすると新しい思いや感情が入ってくる余地が生まれます。
こうして代謝が起こると、エネルギーはスムーズに流れ、心身ともに病気になりにくくなります。
もし無気力でやる気がない状態が続いていたら、そこには自分の心や体からのメッセージが含まれているはずです。何かがうまくまわっておらず、修正を必要としているということ。自分自身と対話してみて、何が原因か、振り返ってみてはいかがでしょうか。